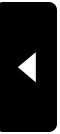2020年07月12日
ちょっと休憩 ランチ
小布施サービスエリアの
かき揚げそば
昼飯を急遽
とることにした
中は
ソーシャルデイスンスが
きちんと取れるように
座席を
セットしてあった
どこの食堂に行っても
ソーシャルディスタンスを
意識している
換気も
十分に出来るように
窓を大きく
開けている
客人としては
安心も買いたいところ
一生懸命
しているよ!
2020年07月01日
父の日
長男の嫁から
ブルーベリーの
実のなっている
木を贈ってくれた
我が家に木はあるのだけれども
収穫する前に
鳥の達に食べられている
今年の
ブルーベリーは
身近に置いておくことにして
しっかりと
実を
収穫してやろうと
思っている
以前には
ほおずきを贈ってくれた
今も元気に育っていて
先日
あまりにも
窮屈そうだったので
大きな鉢に
植え替えてやった
まあ
背丈がどんどん伸びていきますね
実が付くのを
今年も
楽しみにしています
家族では
誕生日には
必ず
プレゼントをしている
いつの時からかはしらないが
我が子が幼児の頃から
祖父にもきちんと
誕生日、父・母の日に
手作りの品を
くれていた
いい子達だ!!
2020年04月26日
年中行事 Ⅲ
九 月
二百十日 農家の厄日ざて天候に注意し平穏無事を祈る二百二十日もまた同じ。
十九日 十八日の夜より此日にかけて祇園祭礼を行ふ。神輿の中町へ遷座するは十三日にして東條村郷社天王山の神庫へ還幸は廿日なり旧藩当時は日本全国著名の大祭にして大門踊馬乗り等の催しありたれど廃藩後は其ことなく、芸者の手踊り等の余典を催すことすら稀である。
彼岸 寺詣り慕參り等春の彼岸に同じ。
十 月
皆神祭 七日八日九日の三日間に亘りて祭を行ふ。就中子供の神様とて八日は遠近よりの參詣客多く当日は松代停車場前には種々の見世物小屋等でき北信著名の大祭である。
月見、太陰歴八月十五日の夜は月見と称し牡丹餅を作り、大根、枝豆等の秋作物を月神に供へる風習が行はれてゐる。
十一月
十日 惠比壽大黒講とて大正十四年より商家はこの日祝売をおし二尺玉以下の煙火数百発を海津城址にて打ち揚ぐ、夫れ以前迄惠比壽講は廿日に行へるが一種の商略関係から近年十日に変更された。
十二月
冬至 此日南瓜を喰ふ習俗あり。
大晦日 年収り、此夜は終夜寝るざるの風習もある。元日に掃除をすれば福の神を掃き出すとて今夜中に掃除を為し置く、門松は二十六七日頃より三十日迄に飾る。各寺院にては百八の鐘を撞く之を除夜の鐘といふ。
この日、今年なくなった家に「お寂しいお年取りです」とお線香を上げに行く風習も残っている。
二年参り(にねんまいり)とは、初詣(はつもうで)の形式の一つである。 大晦日の深夜零時をまたがって神社仏閣に参拝・参詣する事を言う。 年をまたいで行う為にこの名がある。
二百十日 農家の厄日ざて天候に注意し平穏無事を祈る二百二十日もまた同じ。
十九日 十八日の夜より此日にかけて祇園祭礼を行ふ。神輿の中町へ遷座するは十三日にして東條村郷社天王山の神庫へ還幸は廿日なり旧藩当時は日本全国著名の大祭にして大門踊馬乗り等の催しありたれど廃藩後は其ことなく、芸者の手踊り等の余典を催すことすら稀である。
彼岸 寺詣り慕參り等春の彼岸に同じ。
十 月
皆神祭 七日八日九日の三日間に亘りて祭を行ふ。就中子供の神様とて八日は遠近よりの參詣客多く当日は松代停車場前には種々の見世物小屋等でき北信著名の大祭である。
月見、太陰歴八月十五日の夜は月見と称し牡丹餅を作り、大根、枝豆等の秋作物を月神に供へる風習が行はれてゐる。
十一月
十日 惠比壽大黒講とて大正十四年より商家はこの日祝売をおし二尺玉以下の煙火数百発を海津城址にて打ち揚ぐ、夫れ以前迄惠比壽講は廿日に行へるが一種の商略関係から近年十日に変更された。
十二月
冬至 此日南瓜を喰ふ習俗あり。
大晦日 年収り、此夜は終夜寝るざるの風習もある。元日に掃除をすれば福の神を掃き出すとて今夜中に掃除を為し置く、門松は二十六七日頃より三十日迄に飾る。各寺院にては百八の鐘を撞く之を除夜の鐘といふ。
この日、今年なくなった家に「お寂しいお年取りです」とお線香を上げに行く風習も残っている。
二年参り(にねんまいり)とは、初詣(はつもうで)の形式の一つである。 大晦日の深夜零時をまたがって神社仏閣に参拝・参詣する事を言う。 年をまたいで行う為にこの名がある。
2020年04月23日
年中行事 Ⅱ
四 月
三日 桃の節句 雛人形を飾り菱餅を供ふ女子の初子ある家へは近親知己より雛人形を
贈りて祝意を表す。此風一時すたれたるも今また盛んに行はる。昔は三月三日にして松本雛といふもの流行せしこと河原綱徳の著書園柱茶話に見ゆ。
予が幼き比は松木はと云もの行れたり立雛にて譬へば前に紙にて垣の形、うしろに梅の木、或は前に岩あり、うしろに松林といふ 類にて至って廉末なるものなり初節句の時出入りの婆或は取揚婆杯是を持来る雛棚へも上兼る程のものなれど志にて持来るもの故渠等の居る中ばかり飾置程のものなり今時は夫とは違ひて婆等が持来るも裸人形の・・・以下略
八日、釈迦の誕生日なれば寺院は灌仏会を催す。
産土神祭 旧松代藩の士族は白烏神社、其他は祝神社を産土神とす。而して白鳥神社の春季祭は十九日廿日、祝神社は廿三日廿川日に執行し来れるが大正十五年より祭日を統一すべく協議の結果春季は祝神社の四月二十三日、二十四日秋季は白鳥神社の祭日の十月二日三日を採用し両氏子同日に祭典を行ふこととなった。
五 月
八十八夜、農家は種播をして後に遊ぶ風習あれど商家は平日と変わりがない。
廿七日、海軍紀念日。
六 月
端午の節句 菖蒲と蓬とを戸口先の屋根に挿み、且つ軒端に吊す。また餅を撒き菖蒲湯に浴する風あり、男子を挙げたる家にては親戚知己より贈られたる幟、槍、鯉の吹き流し武者人形等を飾り立てて祝ふ。
七 月
土用丑の日、此日は鰻を食ふ風習あり。
八 月
七夕祭 六日の夕暮枝付の青竹に、五色の短冊に七夕の歌など書きたるをつるして飾り瓜、茄子、南瓜等を供へて牽牛、淑女星を祭り七日の午後に至り川へ流す、此朝子供等千曲川へ行きて水泳す。之をおねんぶりを流すといふ。
九日 四万八千日とて虫歌観世音參詣の善男善女にて賑ふ。
盂蘭盆 十三日盆棚を飾り位牌を並べ茄子や胡瓜にて造りたる馬、ササゲ、南瓜、林檎、桔梗、女郎花等を供ふ。而して夕刻迎火とて家の門戸口と墓所にて樺の皮を焚きて墓參をなす。尚新佛ある家へは見舞にゆく等の習はしあり、十四日は焼餅を造りて食し。十六日の朝は佛に供へたるものを市外の所々へ捨て且つ夕方送り火と称し樺の皮を焚きて墓参すること迎え火の時に同じ、この日は麺類を製し佛前に供へて家内一同にて食する習俗がある。昔日は曳燈寵ということ流行せりといふ。
二十七日、御射山祭の神事祝神社におこなわる。この日は朝食に小豆粥を炊き、青萱の箸にて食す乙風習あり。
参考
御射山祭
全国の諏訪神社の本宮である諏訪大社では、上社・下社それぞれに御射山祭が行なわれていました。旧暦の7月下旬、八ヶ岳山麓で巻狩、草鹿射ち、相撲などの武芸が行なわれたほか、里宮では御霊会風の行列が練り歩きました。御射山祭は鎌倉幕府の下知によって信濃国内に領地をもつ御家人すべてが回り番で費用を負担しました。
祭りは武将ばかりでなく一般民衆にも見物が許され、身分の上下を問わない全国規模の大イベントだったのです。下社の御射山祭りは、室町時代に下社大祝の金刺氏が上社によって滅ぼされてからは衰退しましたが、祭典に集まった武士たちによって御射山祭の風習は全国に広められ、「ミサヤマ」と呼ばれる地名や神社が現在でも各地に残っています。
御射山祭は二百十日に先立って山上で忌籠もりをし、いけにえとして動物を捧げることで祟りやすい山の神を鎮めて台風の無事通過を祈願するのが本来の目的だったといいます。
諏訪神はもともと風よけの神として信仰されていました。諏訪大社には薙鎌と呼ばれる風封じの神器があります。これは五行説の「金克木」に基づいた思想であるといわれています。つまり金気である鉄鎌を、木気である木に打ち込むことにより、間接的に木気である風を封じこめようという呪法なのです。
現在の例祭日は8月27日で、上社の御射山社は長野県八ケ岳の山麓にあり、下社は江戸時代初期に八島高原(長野県霧が峰高原内)から秋宮東北五キロ程の山中に移されました。青萱の穂で仮屋を葺き、神職その他が参籠の上祭典を行うので穂屋祭りの名称があります。なお今では農作物の豊穣祈願と二才児の厄除健勝祈願を行うお祭りとなっております。
三日 桃の節句 雛人形を飾り菱餅を供ふ女子の初子ある家へは近親知己より雛人形を
贈りて祝意を表す。此風一時すたれたるも今また盛んに行はる。昔は三月三日にして松本雛といふもの流行せしこと河原綱徳の著書園柱茶話に見ゆ。
予が幼き比は松木はと云もの行れたり立雛にて譬へば前に紙にて垣の形、うしろに梅の木、或は前に岩あり、うしろに松林といふ 類にて至って廉末なるものなり初節句の時出入りの婆或は取揚婆杯是を持来る雛棚へも上兼る程のものなれど志にて持来るもの故渠等の居る中ばかり飾置程のものなり今時は夫とは違ひて婆等が持来るも裸人形の・・・以下略
八日、釈迦の誕生日なれば寺院は灌仏会を催す。
産土神祭 旧松代藩の士族は白烏神社、其他は祝神社を産土神とす。而して白鳥神社の春季祭は十九日廿日、祝神社は廿三日廿川日に執行し来れるが大正十五年より祭日を統一すべく協議の結果春季は祝神社の四月二十三日、二十四日秋季は白鳥神社の祭日の十月二日三日を採用し両氏子同日に祭典を行ふこととなった。
五 月
八十八夜、農家は種播をして後に遊ぶ風習あれど商家は平日と変わりがない。
廿七日、海軍紀念日。
六 月
端午の節句 菖蒲と蓬とを戸口先の屋根に挿み、且つ軒端に吊す。また餅を撒き菖蒲湯に浴する風あり、男子を挙げたる家にては親戚知己より贈られたる幟、槍、鯉の吹き流し武者人形等を飾り立てて祝ふ。
七 月
土用丑の日、此日は鰻を食ふ風習あり。
八 月
七夕祭 六日の夕暮枝付の青竹に、五色の短冊に七夕の歌など書きたるをつるして飾り瓜、茄子、南瓜等を供へて牽牛、淑女星を祭り七日の午後に至り川へ流す、此朝子供等千曲川へ行きて水泳す。之をおねんぶりを流すといふ。
九日 四万八千日とて虫歌観世音參詣の善男善女にて賑ふ。
盂蘭盆 十三日盆棚を飾り位牌を並べ茄子や胡瓜にて造りたる馬、ササゲ、南瓜、林檎、桔梗、女郎花等を供ふ。而して夕刻迎火とて家の門戸口と墓所にて樺の皮を焚きて墓參をなす。尚新佛ある家へは見舞にゆく等の習はしあり、十四日は焼餅を造りて食し。十六日の朝は佛に供へたるものを市外の所々へ捨て且つ夕方送り火と称し樺の皮を焚きて墓参すること迎え火の時に同じ、この日は麺類を製し佛前に供へて家内一同にて食する習俗がある。昔日は曳燈寵ということ流行せりといふ。
二十七日、御射山祭の神事祝神社におこなわる。この日は朝食に小豆粥を炊き、青萱の箸にて食す乙風習あり。
参考
御射山祭
全国の諏訪神社の本宮である諏訪大社では、上社・下社それぞれに御射山祭が行なわれていました。旧暦の7月下旬、八ヶ岳山麓で巻狩、草鹿射ち、相撲などの武芸が行なわれたほか、里宮では御霊会風の行列が練り歩きました。御射山祭は鎌倉幕府の下知によって信濃国内に領地をもつ御家人すべてが回り番で費用を負担しました。
祭りは武将ばかりでなく一般民衆にも見物が許され、身分の上下を問わない全国規模の大イベントだったのです。下社の御射山祭りは、室町時代に下社大祝の金刺氏が上社によって滅ぼされてからは衰退しましたが、祭典に集まった武士たちによって御射山祭の風習は全国に広められ、「ミサヤマ」と呼ばれる地名や神社が現在でも各地に残っています。
御射山祭は二百十日に先立って山上で忌籠もりをし、いけにえとして動物を捧げることで祟りやすい山の神を鎮めて台風の無事通過を祈願するのが本来の目的だったといいます。
諏訪神はもともと風よけの神として信仰されていました。諏訪大社には薙鎌と呼ばれる風封じの神器があります。これは五行説の「金克木」に基づいた思想であるといわれています。つまり金気である鉄鎌を、木気である木に打ち込むことにより、間接的に木気である風を封じこめようという呪法なのです。
現在の例祭日は8月27日で、上社の御射山社は長野県八ケ岳の山麓にあり、下社は江戸時代初期に八島高原(長野県霧が峰高原内)から秋宮東北五キロ程の山中に移されました。青萱の穂で仮屋を葺き、神職その他が参籠の上祭典を行うので穂屋祭りの名称があります。なお今では農作物の豊穣祈願と二才児の厄除健勝祈願を行うお祭りとなっております。
2020年04月20日
年中行事
年中行事
今は忘れてしまったり、おろそかになったりで、季節季節の行事がおろそかになってきている。
一 月
元日、若水を汲み、岸上紳を始めとして紳祀佛閣に恣詣する溝多し。河東獄道敷設以来更級郡八幡紳祀へ參秤する者激琲せるを以て獄道貪欲にては大晦川の晩より元日の朝に百万臨時列車を蓮輯す乙を例ざしてゐる。近年廻嶮を唐し名刺交換台を催し米る。朝食は雑煮餅とすることが一般の習慣である。門松を飾り注連縄を張ることは一般世間と変りがない。旧藩の頃武家方へは東筑摩郡麻績村より門松を持參したものである。之は眞田家が未だ上田城主であった頃からの例なりといふ。
二日、稽古始め仕事始めど俗寸。商佑は初売を祝ふて特別景品付の廉売を行ふ。古米初荷と唱へて商品を逡り出し又は迎へ入れる風習ありたれども今日にては除り行はれず、初夢、書初め等の仇償は依然ざして行はれてゐる。
三日、三ヶ日と称す。神棚に供饌献燈し子供等は歌留多など取りて楽しむ。
四日、新婚の嫁或は婿は里帰りを為し、僧侶は年始の廻禮を行ふ。
六日、六日年取りて夕食を改む。
七日、七種粥を食す『七種なづな唐士の鳥が日本の土地へ渡らぬ先に』と唱へつつ七種を粥に入れて食ふもあり、又単に小豆を混じ之に粥柱とて餅を加ふるもある。
十一日、庫開きとて業を休み鏡併を開く又旧藩の頃武家にては具足開きの祝いを為したものである。
十四日、小正月の歳取りといふ。取り勝とて夕食を早くする風あり。
十五日、門松を撤し一定の箇所に集めて焚く之を左義長といふ。児童は書初を青竹の先端に結び着けて焼き除燼の高く上るを栄誉とす。尚門松の火を家土産となし茶を沸して呑めば感冒に罹らぬと言ひ傅ふ。元松代下田町にては此日道祀紳を祀り、樫の木にて造りたる陰莖の撞木杵を担ぎ廻り戸毎に勧進せるも今はいつしか荒れて了った。
十六日、お賽日といふ。[地獄の釜の蓋も明き、餓鬼も許される]と云はれ番頭、丁稚其他奉公人は何れも休業して遊ぶ。御安町龍泉寺。更級郡西寺尾村典厩寺の焔魔堂等參詣客にて賑ふ。
二十日、二十日正月といふ。新年最終の遊び日とされている。
二 月
二日 奉公人の出代り日であるが現今は定めの日といふものがない。昔は此日出代りの者等が松代木町中央橋辺にて行くか帰るか思案にくれし故に橋の名を思案橋と呼ぶに至った。
節分、焙豆をまきて『福は内鬼は外』と唱ふ。而して共豆を拾ふて自己の年齢の数だけ喰へば壽命延び、之を保存して夏日初めて雷鳴を聞きたる時に喰らへば落雷の厄を免かれると言ひ傳ふ。
初午 赤飯を炊きて稲荷を祀る。竹山随後稲荷社賑ふ。
十一日 紀元節
十五日、涅槃會、各宗寺院に於て〔ヤショウマを作りて參詣人に分つ。
三 月
十日、陸軍紀念日に当たるを以て在郷軍人分曾にては総会を開き紀念式を行ふ。
彼岸 団子を作り佛前に之を供へ菩提寺及び墓所に詣づ。
今は忘れてしまったり、おろそかになったりで、季節季節の行事がおろそかになってきている。
一 月
元日、若水を汲み、岸上紳を始めとして紳祀佛閣に恣詣する溝多し。河東獄道敷設以来更級郡八幡紳祀へ參秤する者激琲せるを以て獄道貪欲にては大晦川の晩より元日の朝に百万臨時列車を蓮輯す乙を例ざしてゐる。近年廻嶮を唐し名刺交換台を催し米る。朝食は雑煮餅とすることが一般の習慣である。門松を飾り注連縄を張ることは一般世間と変りがない。旧藩の頃武家方へは東筑摩郡麻績村より門松を持參したものである。之は眞田家が未だ上田城主であった頃からの例なりといふ。
二日、稽古始め仕事始めど俗寸。商佑は初売を祝ふて特別景品付の廉売を行ふ。古米初荷と唱へて商品を逡り出し又は迎へ入れる風習ありたれども今日にては除り行はれず、初夢、書初め等の仇償は依然ざして行はれてゐる。
三日、三ヶ日と称す。神棚に供饌献燈し子供等は歌留多など取りて楽しむ。
四日、新婚の嫁或は婿は里帰りを為し、僧侶は年始の廻禮を行ふ。
六日、六日年取りて夕食を改む。
七日、七種粥を食す『七種なづな唐士の鳥が日本の土地へ渡らぬ先に』と唱へつつ七種を粥に入れて食ふもあり、又単に小豆を混じ之に粥柱とて餅を加ふるもある。
十一日、庫開きとて業を休み鏡併を開く又旧藩の頃武家にては具足開きの祝いを為したものである。
十四日、小正月の歳取りといふ。取り勝とて夕食を早くする風あり。
十五日、門松を撤し一定の箇所に集めて焚く之を左義長といふ。児童は書初を青竹の先端に結び着けて焼き除燼の高く上るを栄誉とす。尚門松の火を家土産となし茶を沸して呑めば感冒に罹らぬと言ひ傅ふ。元松代下田町にては此日道祀紳を祀り、樫の木にて造りたる陰莖の撞木杵を担ぎ廻り戸毎に勧進せるも今はいつしか荒れて了った。
十六日、お賽日といふ。[地獄の釜の蓋も明き、餓鬼も許される]と云はれ番頭、丁稚其他奉公人は何れも休業して遊ぶ。御安町龍泉寺。更級郡西寺尾村典厩寺の焔魔堂等參詣客にて賑ふ。
二十日、二十日正月といふ。新年最終の遊び日とされている。
二 月
二日 奉公人の出代り日であるが現今は定めの日といふものがない。昔は此日出代りの者等が松代木町中央橋辺にて行くか帰るか思案にくれし故に橋の名を思案橋と呼ぶに至った。
節分、焙豆をまきて『福は内鬼は外』と唱ふ。而して共豆を拾ふて自己の年齢の数だけ喰へば壽命延び、之を保存して夏日初めて雷鳴を聞きたる時に喰らへば落雷の厄を免かれると言ひ傳ふ。
初午 赤飯を炊きて稲荷を祀る。竹山随後稲荷社賑ふ。
十一日 紀元節
十五日、涅槃會、各宗寺院に於て〔ヤショウマを作りて參詣人に分つ。
三 月
十日、陸軍紀念日に当たるを以て在郷軍人分曾にては総会を開き紀念式を行ふ。
彼岸 団子を作り佛前に之を供へ菩提寺及び墓所に詣づ。
2020年01月31日
懸命に生きる
金のなる木
ただ
玄関を通過
外の様子を見る
雪はない
極めていい天気だ
今年はどうなっているのだろう
異常気象
雪が降ってくれないと
狭庭の花や
野菜が
うまく育たない
地球は
怒っているのだろうか・・・
再び
玄関を入って
かくのごとき状況を発見
相方は
「今知ったの?」
だと
この花のないときに
懸命に生きている
植物に感謝
2020年01月29日
山梨のこと
東光寺
ここには
諏訪氏、武田氏の末裔も
祀られている
武田氏は
諏訪氏との
婚姻により
誕生した
武田勝頼(諏訪勝頼)
甲斐武田家第20代当主が
最後の殿様
勝頼の最期は
ご存知のように
見方の(真田信之の義弟)
小山田氏に裏切られて
あえなく最期を遂げる
小山田氏は
真田信之の筆頭家老(1500石)として
明治を迎える
最後まで
主人を助けようとしたのは
真田信之だったという
ここは
訪う人が少ないのかもしれないが
紅葉は見事だ
2020年01月28日
山梨のこと
当初より訪れたかった
武田神社
久しぶりに訪れたが
たくさんの人がいた
駐車場は
空きがなく
少々
待っていたら
入れ替えが
早いので
すぐに駐車できた
武田信玄の
屋敷があったという場所
天下獲りを狙ったところ
神様と言うけれども
日本は
人格神が多い
どうしてなのか
とりわけ
明治以後に
それが
多いように思うが
どうだろう
2020年01月27日
京都のこと
妙心寺の塔頭
退蔵院
京都の案内看板は
このパターンが
すべてで
日本語の部分を
横文字で
表記しているものはない
指示板は
横書きになっているものがほとんど
文化と伝統のある町は
こんな看板が
自然に目に入ってくる
自然にと言うのがいいですね
もし
案内看板の
日本語の部部が
横文字になっていたとしたら
文化と伝統の町には
そぐはないように思うが・・・
八坂神社
2020年01月26日
京都のこと
腹が減ったので
近くのカレー店に
「○○いちカレー」という店
確かに
初めて入ったが
とてもうまかったと言うことを
記憶している
足下を見ているだけでも
実にいろいろある
京都のマンホールの蓋
訳もわからないままに
時間に追われているわけでもないが
そそくさと
写真にした
日本全国の
マンホール写真を
収集している方もいるとか
確かに
面白い
その土地を
象徴しているかのように
蓋がある